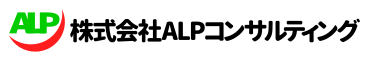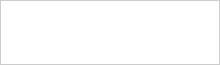日本には中小企業が380万社存在するといわれております。
ということは、中小企業の経営者もそれに近い数いるものと思われます。
つまり、企業経営の経験者、その経験が豊富な人はそれなりの数になります。
中には50年以上にわたり経営者であり続けている方も存在します。
これがいいか悪いかの議論は今回はやめておきます。
しかし、事業承継経験豊富な経営者は皆無と言っていいでしょう。
なので、他社とは言え、事業承継を一緒に考え、一緒に悩んできた経験のある支援者が必要になります。
その支援者はどう選べばいいのか。支援者側に寄せられる苦情として、
「自分の得意分野に偏った支援をされて、抜け落ちている部分がある」
というものがあります。
これは、どの業界でも陥りがちのことなので全否定するものではありません。
例えば、相続(税)対策のため、2世帯住宅を建てようと思って家を見に来ている方に、
自社の家がいかに耐震、耐火性能に優れているかなんていう話をしても響きません。
聞きたいのは、小規模宅地の評価減が受けられるかどうかですので。
まず、小規模宅地の評価減を受けるための要件を説明し、そのためにこんな設計をしますよ!
というところから入っていけば、住宅性能の話にも耳を傾けてもらえるものだと考えます。
話を事業承継支援に戻します。
どんな支援者を選べばいいのか?
全体最適を目指すことができる幅広い経験と幅広い知識。
必要に応じて各専門家を巻き込むコーディネーション能力が必要と考えます。
そして、傾聴することができる人間力。
人間が自分のことはなかなかわからないように、
会社も自社のことは経営者自身では見落としてしまっているところも多々あります。
そこをみつけ、そこも繋いでいくことを支援することも
支援者である事業承継に関するコンサルタントの仕事です。
こんなことを意識して選んだ支援者なら、御社の継続のために、
豊富な経営経験を紡いで社会に会社を残していくための支援をしてくれると思います。
特に中小企業の事業承継においては、承継者に対し非承継者がいる。
この2者が兄弟、親族であったりすることも多々あります。
このような状況を当事者だけであるべき方向にもっていくのは簡単なことではありません。
だからこそ、支援者が必要になると考えます。